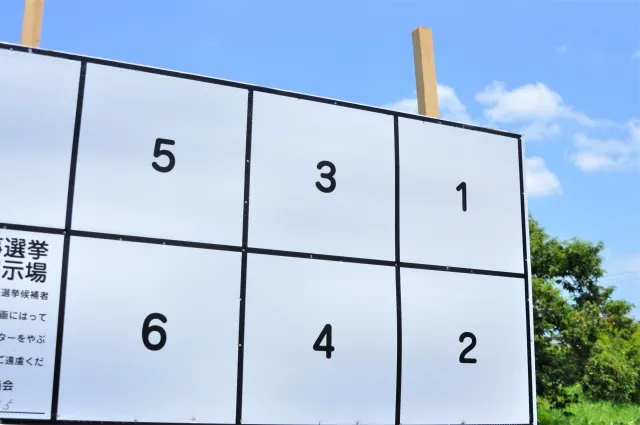日本には、「都市」に関するさまざまな呼び方があります。「政令指定都市」と「地方中枢都市」もその中の一つです。
一見するとどちらも「大きな都市」を指しているように思えますが、実はそれぞれに異なる意味と役割があります。本記事では、「政令指定都市」と「地方中枢都市」の違いを、具体例を使いながらわかりやすく解説していきます。
「政令指定都市」の意味
「政令指定都市」とは、日本の地方自治法に基づいて、内閣の政令によって指定された大きな都市のことです。
指定の条件として、人口が50万人以上であることが求められ、行政や経済の中心として重要な役割を担っています。
この指定を受けた都市は、都道府県が通常行う業務の一部を市が直接行えるようになります。例えば、福祉、都市計画、建築確認などの業務です。
これにより、住民により近い立場で行政サービスを提供できるようになるのが特徴です。
また、「政令指定都市」には、いくつかの行政区(例:札幌市の中央区、北区など)が設けられています。この区は、東京23区とは異なり、市の内部組織として市が管理します。
「政令指定都市」は単に人口が多いだけでなく、地域の経済・文化・行政を支える核として機能していることが求められます。
「政令指定都市」の例文
以下は「政令指定都市」という言葉を使った例文です。都市の成長や役割を表す場面でよく使われます。
- 横浜は、日本で最も人口の多い政令指定都市です。
- 札幌は北海道で唯一の政令指定都市で、行政機能が充実している。
- 名古屋は政令指定都市として、中部圏の経済をけん引している。
- 福岡は九州の玄関口として、政令指定都市にふさわしい規模と機能を持つ。
- 政令指定都市になると、都道府県からの権限が一部移譲される。
「地方中枢都市」の意味
「地方中枢都市」とは、地方創生政策の中で、地域の経済や医療、交通などの中心として期待される都市のことです。
こちらは「政令指定都市」のように法律で明確に定義されているわけではなく、政策上の分類です。
国が策定した「地方中枢拠点都市制度」に基づき、一定の条件(人口20万人以上、大学や病院の有無、企業の集積など)を満たす都市が対象となります。
選定された都市は、国から地方創生のための支援(交付金など)を受けることができます。
重要なのは、「地方中枢都市」は必ずしも大都市である必要はないことです。あくまで、周辺地域との連携を通じて地域全体を引っ張る役割を持つことがポイントです。
「地方中枢都市」の例文
「地方中枢都市」は、地方創生や地域活性化の文脈でよく使われます。以下はその使用例です。
- 仙台は東北地方の地方中枢都市として、多くの企業が集まっている。
- 静岡市は、地域の医療や教育の拠点として地方中枢都市に選ばれている。
- 岡山は地方中枢都市として、周辺の町と連携した都市開発を進めている。
- 地方中枢都市には、交通インフラの整備が求められている。
- 地域全体を支えるために、地方中枢都市の機能強化が図られている。
「政令指定都市」と「地方中枢都市」の違い

「政令指定都市」と「地方中枢都市」の違いは、次のように整理することができます。
| 比較項目 | 政令指定都市 | 地方中枢都市 |
|---|---|---|
| 指定根拠 | 地方自治法 | 地方創生関連の国の政策 |
| 人口要件 | 原則50万人以上 | 原則20万人以上 |
| 権限 | 都道府県からの権限移譲あり | 特別な権限なし |
| 行政区(区制度) | 区を設置 | 区なし |
| 役割 | 大都市圏の中心 | 地域圏の中心(広域支援) |
| 国の支援 | 特別な支援制度はなし | 地方創生推進交付金などあり |
この2つの都市は名前こそ似ていますが、その役割や制度的な背景はまったく異なります。
「政令指定都市」は、地方自治法に基づき、内閣の政令によって正式に指定される法的な制度です。人口50万人以上などの厳しい要件があり、指定を受けると、都道府県が本来担当する業務の一部を担う権限が与えられます。
一方、「地方中枢都市」は、地域を引っ張る中心都市という政策的な位置づけであり、法的な制度ではありません。人口は20万人以上が目安で、周辺の市町村との連携が重視され、地域全体を活性化する役割を担います。
このように、政令指定都市は高度な自治機能を持つ行政都市であり、地方中枢都市は地域の中心として国の支援を受けながら活性化を目指す都市です。都市の規模や役割の違いが、それぞれの制度に反映されています。
「政令指定都市」と「地方中枢都市」の使い分け
「政令指定都市」と「地方中枢都市」は、以下のように使い分けるのが適切です。
① 都市の行政機能が拡大している場合 ⇒「政令指定都市」
政令指定都市は、福祉・都市計画・建築確認など、都道府県レベルの行政機能を担っており、「行政機能の拡大」を示すには適切な言葉です。
② 地域の経済やサービスの中心となっている場合 ⇒「地方中枢都市」
地方中枢都市は、周辺自治体に対して医療・教育・経済などの中核的なサービスを提供する機能を評価されて選定されています。
③ 国からの支援や連携事業が展開されている都市を指す場合 ⇒「地方中枢都市」
地方中枢都市は「国の地方創生施策」の一環として、補助金や連携事業などの支援対象になります。法的権限ではなく、政策上の支援がポイントです。
④ 区が設置されており、市が都道府県並みの事務を行っている場合 ⇒「政令指定都市」
政令指定都市の特徴の一つが「行政区の設置」と「都道府県並みの事務権限」であり、この特徴はまさに制度上の重要ポイントです。
⑤ 地方創生において広域連携の中核を担う都市 ⇒「地方中枢都市」
地方中枢都市には、周辺市町村と連携して地域全体を活性化する役割が期待されています。
補足
例えば、福岡市を「地方中枢都市」と言っても間違いではありませんが、正確には「政令指定都市」です。
福岡市は政令指定都市であり、法的制度としてはこちらが上位概念になります。ただし、地方中枢都市にも選定されているので、場面によってはどちらの表現も使えます。
まとめ
この記事では、「政令指定都市」と「地方中枢都市」の違いを解説しました。
「政令指定都市」は行政的な権限を強化された都市、「地方中枢都市」は地域連携を支える政策的な拠点です。
それぞれの言葉の意味を正しく理解し、適切に使い分けるようにしましょう。
本記事を読んだ後は、以下の関連記事もおすすめです。