
日本語には、同じ読み方でも意味が異なる言葉があります。特に「異字同訓」と「同音異義語」は、似ているようで視点が異なるため、混同しやすいテーマです。
どちらも日本語における学習では重要なため、理解することで表現力が一段と高まります。本記事では、それぞれの意味と違いを分かりやすく解説します。
「異字同訓」の意味
「異字同訓(いじどうくん)」とは、異なる漢字で表記されるにもかかわらず、同じ訓読みを持つ語のことを指します。
つまり、同じ音で読み上げることができるけれども、使われる漢字や意味が異なる言葉のことです。
たとえば、「会う」と「遭う」はどちらも「あう」と読みますが、「会う」は人と顔を合わせること、「遭う」は思いがけない出来事に出くわすことを表します。
また、「取る」「採る」「捕る」なども「異字同訓」にあたります。読み方は同じ「とる」ですが、対象やニュアンスが異なります。「取る」は物を手にすること、「採る」は意見や方針を選択すること、「捕る」は魚や動物をつかまえることを指します。
このように、「異字同訓」は、同じ音でも文脈によって正しい漢字を使い分ける必要がある言葉の分類を指します。
「異字同訓」の具体例
以下に、「異字同訓」の具体例を挙げます。
- 会う(人と顔を合わせる)/遭う(偶然出会う、不幸な出来事に直面する)
- 見る(目で見る)/診る(病人を診察する)/観る(映画や舞台を鑑賞する)
- 上げる(物を高いところへ持っていく)/挙げる(例や功績を示す)
- 聞く(耳で音を感じ取る)/訊く(質問する)
これらの例から分かるように、読み方は同じでも、使う漢字によって意味が細かく分かれます。
日常生活でも頻繁に使われるため、文脈を正しく理解し、相手に誤解されない漢字を選ぶことが大切です。
特に公的な文書やビジネス文書では、適切な漢字表記を用いることで正確さが増し、読み手に安心感を与えることができます。
「同音異義語」の意味
「同音異義語(どうおんいぎご)」とは、発音は同じでも意味が異なる語全般を指す言葉です。ここでは漢字の違いに限らず、ひらがなやカタカナの語も含まれます。
たとえば、「はし」という音を思い浮かべてみましょう。この音には、「橋」「箸」「端」といった異なる意味の言葉があります。どの「はし」なのかは文脈によって理解されるのです。
さらに「こうしょう」という音も、「交渉」「高尚」「公称」など多くの漢字で表され、意味がそれぞれ異なります。
このように、一つの読みが複数の語に対応するのが「同音異義語」の特徴です。つまり、「同音異義語」は、音に注目した分類であり、漢字表記だけではなく、外来語や和語にも見られる現象です。
「同音異義語」の具体例
以下に、「同音異義語」の具体例を挙げます。
- はし → 橋(川にかかる構造物)、箸(食事に使う道具)、端(物の先や境目)
- かんこう → 観光(旅行など)、刊行(出版すること)、慣行(慣れ親しんだ習わし)
- ほしょう → 保証(約束や確約)、保障(安全や権利の保護)、補償(損害や不足分を埋めること)
- きじ → 記事(新聞の記事)、生地(布や生地)、雉(鳥の一種)
これらは、会話の中では聞き分けができず、文脈から理解するしかありません。
文章で表記する際は漢字を使うことで意味を区別できますが、ひらがな表記にすると誤解を招く可能性があります。
そのため、状況や相手に応じて正確な表記を心がける必要があります。
「異字同訓」と「同音異義語」の違い
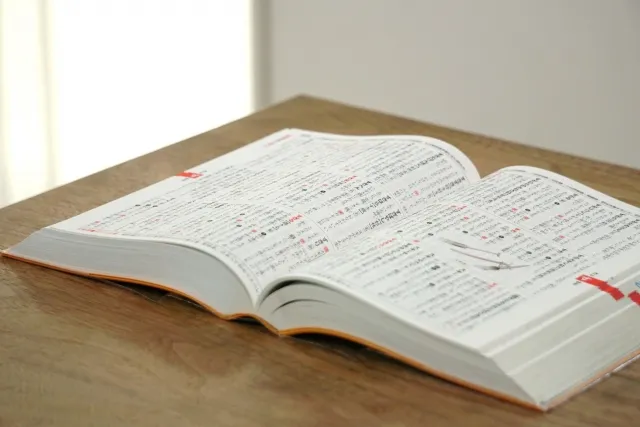
「異字同訓」と「同音異義語」の違いは、次のように整理することができます。
| 項目 | 異字同訓 | 同音異義語 |
|---|---|---|
| 定義 | 異なる漢字で同じ訓読みを持つ語 | 発音が同じで意味が異なる語 |
| 例 | 会う/遭う/合う | 橋/箸/端 |
| 着目点 | 漢字の違い | 音(読み)の一致 |
| 範囲 | 漢字語に限定 | 漢字・ひらがな・カタカナ |
| 関係 | 同音異義語の一種 | 異字同訓の上位概念 |
両者は、どちらも「同じ読み方を持つ」という共通点はありますが、注目する視点が異なります。
「異字同訓」は、異なる漢字で表記されながら同じ訓読みを持つ語を指します。たとえば、「載せる」と「乗せる」はどちらも「のせる」と読みますが、意味や用法はそれぞれ異なります。
つまり、同じ訓読みであっても正しい漢字を使い分ける必要があるのが「異字同訓」です。
一方の「同音異義語」は、音が同じで意味が異なる語の総称です。こちらは漢字に限らず、ひらがなやカタカナの語も含まれます。
たとえば、「かみ」には「神(神様)」と「紙(手紙やプリント用紙)」という異なる意味がありますが、どちらを指すかは文脈を見なければ判断できません。このように、音に着目して分類されるのが「同音異義語」です。
まとめると、「異字同訓」は漢字の訓読みの違いに焦点を当てた狭い分類であり、「同音異義語」は音に注目した広い分類です。そのため、「異字同訓」は「同音異義語」の一部に含まれると考えると理解しやすいです。
「異字同訓」と「同音異義語」の使い分け
それでは、実際に両者の使い分けを理解できたかどうか確認しておきましょう。次の例は「異字同訓」と「同音異義語」のどちらに当てはまるでしょうか?
- 「賭ける」と「掛ける」
- 「赤」と「垢」
- 「閉める」と「締める」
- 「描く」と「書く」
- 「公演」と「公園」
1番、3番、4番は、異なる漢字で同じ訓読みを持つ語なので「異字同訓」、2番と5番は、音は同じでも意味が全く異なる語なので「同音異義語」にあたります。
このように、漢字の訓読みの使い分けが問題になる場合は「異字同訓」、漢字に限らず音が同じ語を広くまとめて扱う場合は「同音異義語」と考えると整理しやすいです。
まとめ
今回は、「異字同訓」と「同音異義語」の違いを解説しました。
「異字同訓」は、異なる漢字で同じ訓読みを持つ語のことを指し、「同音異義語」は発音は同じでも意味が異なる語のことを指します。
この違いを理解することで、文章力や読解力の向上にもつながるでしょう。





