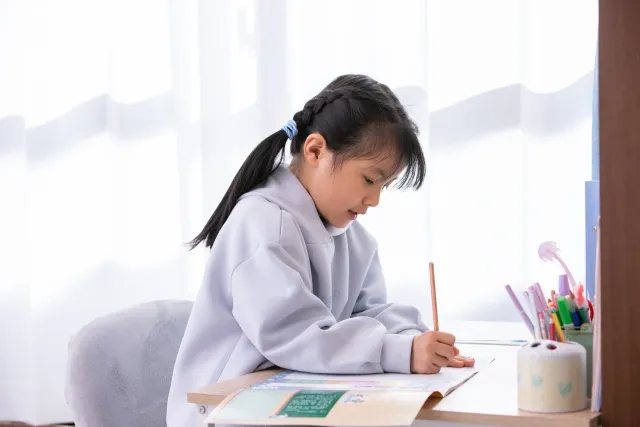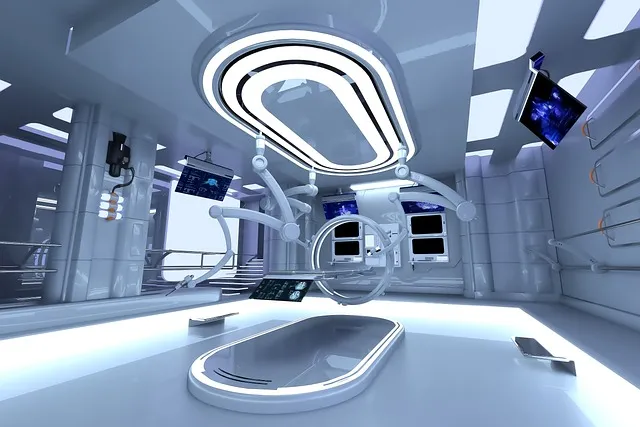和食の中でも、家庭料理で親しまれているのが「煮浸し」と「揚げ浸し」です。どちらも食材をだしに浸して味を含ませる料理ですが、その違いをご存知でしょうか?
一見よく似ているため混同されがちですが、それぞれの特徴を押さえておくと料理の理解が深まります。本記事では、「煮浸し」と「揚げ浸し」の違いを分かりやすく解説していきます。
「煮浸し」の意味
「煮浸し(にびたし)」とは、野菜や豆腐などの食材をだし汁で煮て、そのまま浸して味を含ませる料理のことです。
下ゆでをしてから煮る場合もありますが、基本的には油を多く使わず、さっぱりとした仕上がりになるのが特徴です。
調理の際には昆布やかつお節でとった和風だしが使われ、醤油やみりんで味を調えます。食材がだしをしっかり吸い込むため、冷やしてもおいしく食べられます。
たとえば、小松菜やほうれん草などの葉物野菜は煮浸しの代表的な食材です。夏にはオクラやトマトなどを使った冷やし煮浸しもよく作られ、季節を問わず家庭で親しまれています。
油っこさが少ないので健康的で、素材そのものの持ち味を生かせる調理法といえるでしょう。
「煮浸し」の例文
- 祖母は、夕食に小松菜の煮浸しを用意してくれました。
- 夏の昼食には、冷やしたオクラの煮浸しが食欲をそそる。
- 弁当のおかずに、しっかり味の染みたナスの煮浸しを入れた。
- 健康を気にする父は、油を使わない煮浸しを好んで食べている。
- 友人は、だしの取り方一つで煮浸しの味が変わると教えてくれた。
「揚げ浸し」の意味
「揚げ浸し(あげびたし)」とは、食材を油で揚げた後に、熱いうちにだし汁へ浸して味を染み込ませる料理です。
揚げることで食材に香ばしさやコクが加わり、だしとの相性が一層引き立ちます。ナスやピーマンなど、油との相性がよい野菜がよく使われ、ジューシーで食べごたえのある仕上がりになるのが特徴です。
また、揚げ浸しは時間が経つほど味が染み込み、冷めてもおいしいのが魅力です。揚げる手間はかかりますが、その分風味が増し、食欲をそそる料理に仕上がります。
ご飯のおかずはもちろん、酒の肴としても人気が高く、居酒屋でも定番の一品として提供されます。
「揚げ浸し」の例文
- 夕食にナスの揚げ浸しを作り、食卓が一気に華やかになった。
- 夏祭りの翌日、冷蔵庫に残っていたピーマンの揚げ浸しをつまんだ。
- 弟はジューシーな揚げ浸しが好きで、特にかぼちゃを好んで食べる。
- 居酒屋で頼んだ揚げ浸しは、香ばしい香りが食欲をそそった。
- 揚げ物が苦手な友人も、あっさりした揚げ浸しなら食べられると言った。
「煮浸し」と「揚げ浸し」の違い

「煮浸し」と「揚げ浸し」の違いは、次のように整理することができます。
| 項目 | 煮浸し | 揚げ浸し |
|---|---|---|
| 調理法 | だしで煮て味を含ませる | 素揚げしてだしに浸す |
| 油の使用 | 少ない/控えめ | 多い(揚げ油を使用) |
| 風味 | さっぱり・上品 | 香ばしくコクがある |
| 食感 | 軽やかで柔らかい | 油を吸って濃厚・ジューシー |
| 代表例 | 小松菜の煮浸し、オクラの煮浸し | ナスの揚げ浸し、ピーマンの揚げ浸し |
両者の違いは、主に調理方法と風味の点にあります。
「煮浸し」はだし汁で煮て味を含ませるため、油分が少なくさっぱりとした仕上がりです。一方で「揚げ浸し」は食材を揚げてからだしに浸すため、香ばしさやコクが加わり、濃厚な味わいになります。
また、食感にも違いがあります。「煮浸し」は軽やかで柔らかい口当たりですが、「揚げ浸し」は油を吸ったジューシーな食感が楽しめます。
さらに、家庭での調理の手軽さにおいても違いがあり、「煮浸し」のほうが短時間で作りやすいという利点があります。「揚げ浸し」は油を使うため少し手間がかかりますが、その分満足感の高い料理になります。
このように、両者は同じ「だしに浸す料理」でありながら、工程の違いによって味わいや印象が大きく異なることが分かります。
「煮浸し」と「揚げ浸し」の使い分け
それでは、実際に両者をどのように使い分ければよいのでしょうか?以下に、場面ごとの使い分け方を簡単に示します。
① さっぱり食べたい場合 ⇒「煮浸し」
食欲が落ちやすい夏や、油分を控えたいときは「煮浸し」を使います。だしの優しい味が素材に染み込み、冷やしてもおいしく食べられるのが魅力です。
② コクのあるおかずが欲しい場合 ⇒「揚げ浸し」
ご飯のおかずやお酒のお供に、食べごたえが欲しいときは「揚げ浸し」を使います。揚げることで香ばしさが増し、だしと調和して濃厚な味わいが楽しめます。
③ 調理の手軽さを重視する場合 ⇒「煮浸し」
時間がないときや手早く作りたいときは「煮浸し」を選びます。油を使わず、材料を下ゆでして煮るだけで完成するため、家庭料理として簡単に取り入れられます。
※誤解しがちなのは、「煮浸し」が必ずしも薄味ではなく、「揚げ浸し」も必ずしも重たい料理ではないという点です。味付けや食材の組み合わせ次第で調整できるため、場面に合わせて柔軟に使い分けるとよいでしょう。
まとめ
この記事では、「煮浸し」と「揚げ浸し」の違いを解説しました。両者は同じく「だしに浸す」料理ですが、調理方法の違いによって風味や食感が大きく変わります。
さっぱりと食べたいときには「煮浸し」、しっかりとしたコクを楽しみたいときには「揚げ浸し」と、状況に応じて選ぶことで料理の幅が広がります。家庭料理としても作れるため、それぞれの特徴を知り、食卓に合った一品を取り入れてみてください。
※本記事を読んだ後は、以下の関連記事もおすすめです。