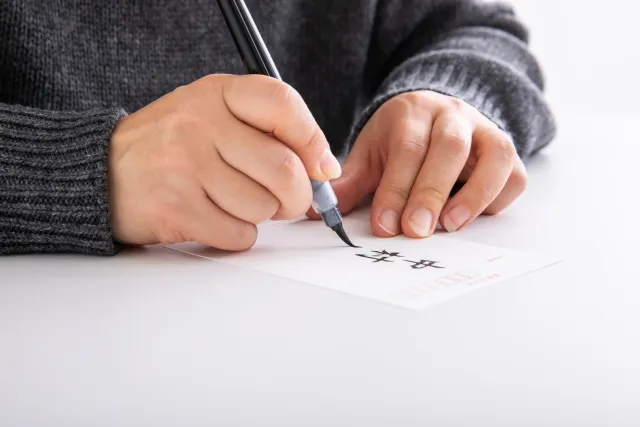「所轄」と「管轄」は、どちらも行政手続きをする際に使われる言葉です。しかし、似た意味を持つものの、使われる基準や範囲には違いがあります。
特に社会保険や労務手続きの場面では、どちらを使うかで手続き先が変わる場合もあります。本記事では、それぞれの意味を具体例を交えながらわかりやすく解説していきます。
「所轄」の意味
「所轄(しょかつ)」とは、労働者が勤務する事業所の所在地を基準に、その事業所に関する手続きを担当することを指します。
社会保険や労務の手続きでは、会社の所在地に応じて、ハローワークや労働局が担当します。たとえば、勤務先の所在地が新宿にある場合、「所轄」のハローワークは新宿となります。
育児休業給付金の申請なども、労働者自身ではなく、勤務する事業所を通じて「所轄」の行政機関に届け出ます。
このように、「所轄」は、個人の居住地ではなく事業所の所在地を基準に管理・手続きが行われる点が特徴です。社会保険労務士の学習では、この「事業所基準」を理解することが重要です。
「所轄」の例文
- 会社が渋谷区内なので、所轄のハローワークは渋谷となる。
- 育児休業給付金は、勤務先を通じて所轄の労働局に申請する。
- 会社の労働保険の書類は、所轄の職安に提出する必要がある。
- 所轄の警察署が、地域の安全管理を担当している。
- 本社所在地を基準に、所轄の労働局に報告書を提出した。
「管轄」の意味
「管轄(かんかつ)」とは、労働者本人の居住地を基準に、その地域の手続きや事務を担当することを指します。
主に個人を対象とした申請や手続きの際に使われる言葉です。たとえば、失業給付の申請や求職申し込みは、居住地を担当する管轄のハローワークで行います。
「管轄」は、事業所所在地を基準とする「所轄」と異なり、個人の住所に基づいた管理・手続きを重視する概念です。
社会保険や雇用保険の実務では、労働者本人の住所を基準に手続きを行う際に、この「管轄」の理解が重要となります。
「管轄」の例文
- 失業給付の申請を、管轄のハローワークで行った。
- 居住地を管轄する職安で、求職登録の手続きを進めた。
- 転居に伴い、管轄の市役所で住民票を移動した。
- 個人の年金手続きは、住所地を管轄する年金事務所で行われる。
- 住所変更に関する届出は、管轄の行政窓口で対応してもらった。
「所轄」と「管轄」の違い

「所轄」と「管轄」の違いは、次のように整理することができます。
| 区分 | 所轄 | 管轄 |
|---|---|---|
| 基準 | 事業所所在地 | 被保険者の住所 |
| 意味 | 会社を担当する範囲 | 個人を担当する範囲 |
| 関係対象 | 勤務先 | 労働者本人 |
| 手続き例 | 育児休業給付金など | 失業給付・求職申込 |
| 具体例 | 渋谷の会社 → 渋谷の職安 | さいたまの住所 → さいたまの職安 |
「所轄」と「管轄」は、いずれも「担当する・取り締まる」という意味を持つ言葉ですが、使われる場面や基準には明確な違いがあります。
特に社会保険労務士試験や労務実務では、「ハローワーク(公共職業安定所)」における使い分けが重要です。
まず「所轄」とは、労働者が勤務する事業所の所在地を基準に、その地域の事務処理を取りまとめることを指します。
育児休業給付金の申請や雇用保険関係の書類提出などは、勤務先を通じて「所轄」のハローワークに手続きを行います。
一方で、「管轄」とは、労働者本人の居住地を基準に、その地域の事務処理を取りまとめることを意味します。
失業給付の申請や求職の申し込みなどは、居住地を担当する「管轄」のハローワークで行います。
具体例で説明すると、勤務先が渋谷区、居住地がさいたま市の場合、育児休業給付金の申請は渋谷の「所轄」のハローワークで行い、失業給付の申請や求職の申し込みはさいたま市「管轄」のハローワークで手続きをします。
このように、どちらも行政手続きの対象を示す言葉ですが、「所轄」=事業所基準、「管轄」=住所基準で区別されます。
したがって、労務手続きの場面では、どちらのハローワークに提出すべきかを判断するために、両者の基準を正しく理解しておくことが大切です。
「所轄」と「管轄」の使い分け
それでは、実際に両者をどのように使い分ければよいのでしょうか?以下に、場面ごとの使い分け方を簡単に示します。
① 勤務先や会社の手続きの場合 ⇒ 「所轄」
勤務先を基準にした行政手続きや書類提出は、「所轄」を使います。育児休業給付金や労働保険関係書類の提出などが該当します。
② 個人の居住地に関わる場合 ⇒ 「管轄」
失業給付の申請や求職申し込み、住民票や年金手続きなどは、住所を基準にした「管轄」が適切です。
③ 行政機関の権限範囲を示す場合 ⇒ 「所轄」「管轄」両方
警察署や税務署など、地域の範囲を管理する場合には、文脈に応じて「所轄」または「管轄」を使います。
まとめ
この記事では、「所轄」と「管轄」の違いを解説しました。
「所轄」は事業所所在地を基準に行政機関が管理する範囲を指し、「管轄」は個人の住所を基準に管理する範囲を指します。
実際に手続きを行う際には、どちらの基準で進めるかを理解することが重要です。
※本記事を読んだ後は、以下の関連記事もおすすめです。