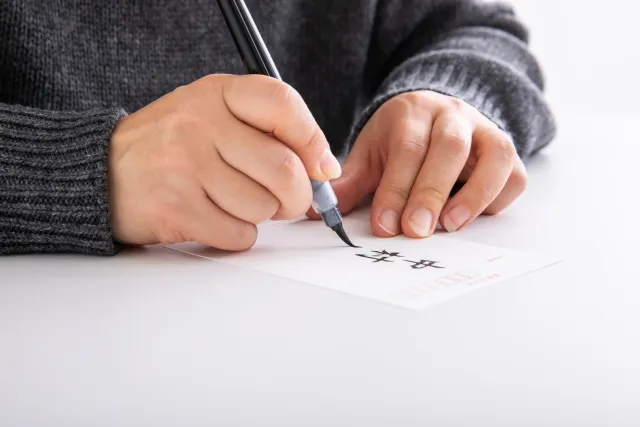「寸志」と「志」は、どちらも贈り物や謝礼の場面で使われる言葉です。しかし、どのような状況で使うかによって意味やニュアンスが大きく異なります。
誤った使い方をすると、相手に不適切な印象を与えてしまうこともあります。本記事ではそれぞれの意味を、具体例を使いながらわかりやすく解説していきます。
「寸志」の意味
「寸志(すんし)」とは、「わずかではあるが、心を込めた贈り物」という意味を持つ言葉です。
「寸」は「少し」「わずか」を表し、そこから転じて、金額の多少にかかわらず、へりくだった表現として用いられます。
たとえば、会社で上司が部下に感謝の気持ちを示して金品を渡す際や、ちょっとした謝礼・心付けを表すときに「寸志」と表記します。
ここで重要なのは、「寸志」と書いてあっても必ずしも少額であるとは限らない点です。実際の金額にかかわらず、「ささやかな気持ち」という謙譲のニュアンスを含めるために使われます。
一方で、「寸志」は目下の立場から目上の人へ渡す場合や、弔事での使用は不適切とされています。現代では「心付け」とほぼ同じ意味で扱われることも多く、ビジネスや日常のちょっとしたお礼の場面で便利に使える表現です。
「寸志」の例文
- 上司が部下に、年度末の労をねぎらうために寸志を渡した。
- 社長が社員に、プロジェクト完了のお礼として寸志を手渡した。
- 顧客への対応に尽力した社員に対して、上司が寸志を渡した。
- 部署の責任者が、研修を手伝った部下に寸志としてお菓子を渡した。
- 上司がアルバイトに、繁忙期の勤務に対する感謝の気持ちとして寸志を渡した。
「志」の意味
「志(こころざし)」とは、本来「心に思うこと」「気持ち」などを意味する言葉です。そこから転じて、現代では主に弔事や法要での香典返しの表書きとして使用されます。
仏式では「志」とするのが一般的で、地域によっては「満中陰志」(主に関西以西)、神式では「偲び草(しのびぐさ)」、キリスト教では「記念品」などと表記が分かれることがあります。贈る相手の宗教や地域の慣習に合わせることが大切です。
掛け紙には黒白・黒銀・黄白の水引が使われ、表書きは薄墨(うすずみ)で書くのが基本です。薄墨には「涙でにじんだように見せる」「深い悲しみを表す」という意味が込められています。
なお、「志」はあくまで弔事におけるフォーマルな表現であり、日常的な謝礼や慰労の場面では使われません。感謝の意を丁寧に伝えるための、格式ある言葉として理解しておくとよいでしょう。
「志」の例文
- 葬儀の香典返しに、品物とともに「志」と書かれた掛け紙が添えられていた。
- 四十九日の法要後、遺族が「志」として記念品を親族に渡した。
- 仏式の法事では、返礼品に「志」と表書きするのが一般的である。
- 関西地方では、四十九日後の返礼に「満中陰志」と書くこともある。
- お世話になった方へ、弔事の贈り物として「志」と書かれた品を送った。
「寸志」と「志」の違い

「寸志」と「志」の違いは、次のように整理することができます。
| 項目 | 寸志 | 志 |
|---|---|---|
| 意味 | わずかばかりの謝礼、心付け | 心ばかりの贈り物、感謝の気持ち |
| 主な場面 | 目上から目下への謝礼・慰労・心付け | 香典返し、法要、弔事 |
| ニュアンス | 謙譲的・ややカジュアル | 厳粛・フォーマル |
| 掛け紙 | のし紙に「寸志」と書く | 水引・薄墨で「志」と書く(宗教・地域により異なる) |
| 関連語 | 心付け、粗品 | 満中陰志、偲び草(神式)、記念品(キリスト教) |
「寸志」と「志」の違いは、主に贈る相手・場面・フォーマリティにあります。
「寸志」は、目上の人が目下の人に感謝や慰労を示す日常的な謝礼で、金額の多寡に関わらず謙譲の意味を含みます。
一方の「志」は、弔事や法要における正式な表書きとして使われるため、フォーマルで厳粛なニュアンスがあります。
また、「寸志」は口頭や日常のやり取りで使いやすく、心付けや粗品と同義で扱われることがあります。
しかし、「志」は葬儀や四十九日など特定の儀式に限定される傾向が強く、地域や宗教によって表書きの形式も変わります。
たとえば、関西では「満中陰志」と書くことがありますし、神式では「偲び草」、キリスト教では「記念品」とされます。
さらに掛け紙の水引や文字色も異なります。「寸志」は特に決まった水引の色や書き方はありませんが、「志」は黒白・黒銀・黄白の水引が使われ、薄墨で書くことが慣例です。
薄墨には悲しみを表す意味が込められており、葬儀の場にふさわしい表現となっています。
このように、両者は見た目や字面は似ていますが、用途や場面によって使い分けが必要です。
「寸志」と「志」の使い分け
それでは、実際に両者をどのように使い分ければよいのでしょうか?以下に、場面ごとの使い分け方を簡単に示します。
①目上から目下へ謝礼や慰労を渡す場合⇒「寸志」
目上の立場から部下や関係者にお礼を渡すときは「寸志」を使います。少額であっても謙譲表現として心付けの意味を伝えることができます。
②弔事や法要での返礼の場合⇒「志」
葬儀、四十九日、法要などの弔事の場では「志」を使います。地域や宗教に応じて表書きが変わることがありますので、事前に確認することが大切です。
③日常のお礼やちょっとした贈り物の場合⇒「寸志」
営業や挨拶回り、サービスへのお礼など、形式ばらない感謝の気持ちを伝える場合は「寸志」を使います。「粗品」や「心付け」と同義で使うことも可能です。
※誤解を防ぐポイントとして、「寸志」は弔事では使わない、「志」は日常のお礼では避ける、という基本ルールを覚えておくと安心です。
まとめ
この記事では、「寸志」と「志」の違いを解説しました。
「寸志」は目上から目下への謝礼や心付けに使う謙譲表現であり、「志」は葬儀や法要の返礼として用いるフォーマルな表書きです。
用途や場面に応じて正しく使い分けることで、相手に適切な気持ちを伝えることができます。
※本記事を読んだ後は、以下の関連記事もおすすめです。