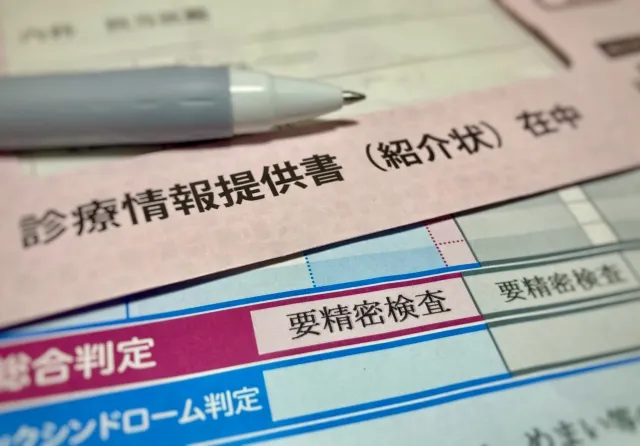ビジネスや商取引の現場では、普段あまり耳にしない言葉が使われることがあります。その中でも、「仕切」と「建値」は価格に関わる重要な用語としてよく登場します。
特に、流通やメーカーとの取引を経験する人にとっては、この二つの言葉の理解が欠かせません。そこで本記事では、「仕切」と「建値」の意味の違いを、具体例を交えてわかりやすく解説します。
「仕切」の意味
「仕切(しきり)」とは、商取引において実際に決まった取引価格を指す言葉です。
語源は「取り仕切る=まとめる」から来ており、売り手と買い手が交渉をして最終的に「この値段でまとめよう」と合意した金額を表します。
流通業界では特に、メーカーが卸売業者に商品を出すときの価格を「仕切値」と呼ぶことが多いです。ただし、卸売業者が小売業者に提示する価格をそう呼ぶ場合もあり、使う立場によって意味が変わるケースがあるため注意が必要です。
たとえば、メーカーが卸に対して1個100円で商品を提供した場合、それが仕切値になります。卸が小売に売るときには、掛け率や販売条件によって価格が変わり、場合によってはその金額も「仕切値」と呼ばれることがあります。
つまり「仕切」は、立場によって見え方が変わる実際の価格を指すということです。
「仕切」の例文
- 営業部長は、取引先に提示する仕切価格をもう一度見直すよう指示した。
- 卸売業者は、仕切値を下げてでも在庫を早く処分しようと考えていた。
- 交渉の結果、予定よりも安い仕切価格で仕入れることができた。
- 小売店は、仕切価格を確認したうえで販売価格を決定した。
- 新商品は仕切値が高めに設定されており、利益を出すには工夫が必要だった。
「建値」の意味
「建値(たてね)」とは、メーカーや生産者が市場に向けて発表する基準価格を指します。
語源は「値を建てる=価格を立てる」から来ており、市場全体に対して「この商品はこの金額が目安です」と示す役割を持っています。
主に、鉄鋼・非鉄金属・石油・セメントなどの素材産業で用いられ、メーカーが月ごとに「建値」を発表するのが一般的です。これにより、卸売業者や小売業者は、その建値を参考にして価格を決めます。
ただし、「建値」はあくまでも目安であり、実際にその金額で取引されるとは限りません。需給状況や取引条件によって実際の価格は変動し、そこに交渉が加わって「仕切」として成立するわけです。
したがって、「建値」は基準価格、「仕切」は実勢価格と理解すると分かりやすいでしょう。
「建値」の例文
- 鉄鋼メーカーが来月の建値を発表し、業界全体の動向が注目された。
- 仕入れ先の建値が上がったため、販売価格の見直しを迫られた。
- 商社Aは、建値を参考にして、顧客との価格交渉を始めた。
- 石油業界では、建値の改定がニュースとして大きく取り上げられることが多い。
- メーカーが建値を据え置いたため、市場では安堵の声が広がった。
「仕切」と「建値」の違い

「仕切」と「建値」の違いは、次のように整理することができます。
| 項目 | 仕切(仕切値) | 建値 |
|---|---|---|
| 語源 | 取り仕切る=まとめる | 値を建てる=基準を立てる |
| 意味 | 実際に成立した取引価格 | メーカーが発表する基準価格 |
| 主な対象 | メーカー→卸(場合により卸→小売) | メーカー→卸・市場全体 |
| 決定方法 | 交渉や需給で変動 | メーカーが一方的に提示 |
| 性格 | 実勢価格・現場依存 | 相場の指標・目安 |
両者の関係を理解するには、「建値」はあくまでメーカーが示す旗印の価格であり、「仕切」は交渉の結果として実際に成立する価格という点を押さえることが重要です。
たとえば、鉄鋼メーカーが「建値を1トンあたり10万円」と発表したとします。これはあくまで市場に示された目安であり、実際に卸売業者がその価格で仕入れるかどうかは交渉次第です。
結果的に9万8千円でまとまれば、それが仕切値となります。逆に、需給が逼迫していれば建値通り、もしくはそれ以上で取引されることもあります。
このように、「建値」は基準として市場に立てられる価格、「仕切」は現実の取引における決着価格です。ただし、実務上は建値がそのまま仕切値として使われる場合もあり、両者が同じ意味で扱われるケースも少なくありません。
「仕切」と「建値」の使い分け
それでは、実際に両者をどのように使い分ければよいのでしょうか?以下に、場面ごとの使い分け方を簡単に示します。
① メーカーが提示する価格の場合 ⇒ 「建値」
メーカーや生産者が「来月の販売価格は○○円」と発表する場合は「建値」を使います。これは、基準価格を市場に示す行為だからです。
② 卸が実際に仕入れた価格の場合 ⇒ 「仕切」
卸売業者がメーカーから商品をどの金額で仕入れたかを示すときは「仕切」を使います。これは、交渉の結果成立した取引価格だからです。
③ 交渉で決まった実際の価格を表す場合 ⇒ 「仕切」
小売店が卸から仕入れるときや、条件を交渉して実際に決まった金額を話すときも「仕切」を使います。基準価格ではなく現場で確定した数字だからです。
※「建値=基準」「仕切=実際」という軸で考えると整理しやすいです。両者が一致するケースもありますが、文脈によってどちらを指しているかを意識すると混乱を避けられます。
まとめ
本記事では、「仕切」と「建値」の違いを解説しました。
「建値」は、メーカーが市場に向けて提示する基準価格であり、「仕切」は、交渉の末に実際に決まった取引価格です。両者は似ているようで役割が異なりますが、実務上は同じ数字になる場合もあります。
重要なのは、「建値=旗印」「仕切=決着した金額」と押さえておくことです。そうすることで商談の理解が深まり、誤解なく価格の話ができるようになるでしょう。
※この記事を読んだ後は、以下の関連記事もおすすめです。