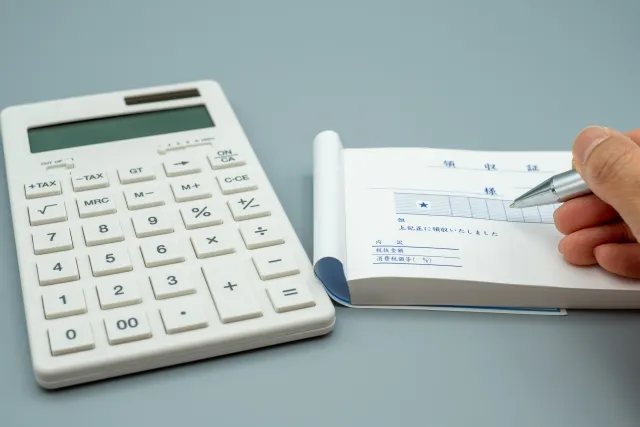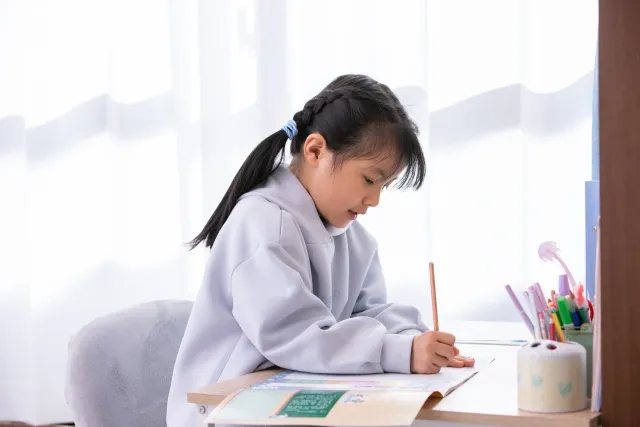
「小児」と「児童」という言葉は、似ているようで微妙に意味が異なります。両者は、使う場面や文脈によって使い分けが求められます。
本記事では、これらの言葉の違いを明確にし、正しい使い方を解説していきます。違いを理解すれば、日常生活で的確な表現ができるようになるでしょう。
「小児」の意味
「小児(しょうに)」とは、一般に乳児から小学生くらいの子どもを指します。
漢字の「小」は「小さい」や「幼い」を意味し、「児」は「子ども」を意味します。そのため、文字通り「小児」は「小さな子ども」を指す表現です。
「小児」は、主に医療や法律、保険などの分野で使われることが多く、日常的に使われる場面は少ないです。具体的な年齢の定義はありませんが、多くは15歳未満の子どもを指すことがほとんどです。
「小児」の具体例
医療現場では「小児科」という診療科が存在します。小児科では、乳児や子どもを対象にした診療が行われ、風邪や発熱などの症状を診るだけでなく、予防接種や発育のチェックも行います。
また、「小児保健」という言葉もあり、子どもが健やかに成長できるよう支援する分野もあります。他には、「小児用薬品」など、子ども向けの製品や医療に関する用語としても登場します。
このように「小児」という言葉は、乳児や子どもを指すことが多く、特に医療や保健、福祉の分野で重要な役割を果たします。
「小児」の例文
- 小児科に行くときは、事前に予防接種を受けておくことが大切です。
- 小児の健康管理には、定期的な健康診断が必要です。
- 小児用の薬を選ぶ際は、年齢に適したものを使うべきです。
- この病院では、小児の治療に特化した専門医が診察を行っています。
- 小児の食事は、栄養バランスを考慮して調整しましょう。
「児童」の意味
一方、「児童(じどう)」とは、主に子どもを指す言葉で、特に小学校に通っている年齢の子どもを指します。
日本語における「児童」は、通常、成人に達していない年齢の子どもを意味し、特に6歳から12歳くらいの年齢層に使われることが一般的です。この年齢層は、小学校に通う子どもたちが当てはまります。
「児童」の具体例
「児童」は義務教育の一環として使われることが多く、学校や教育機関との関連が深い言葉です。例えば、「児童向け図書」や「児童会活動」など、学校での活動に関してよく使われます。
また、「児童養護施設」は、家庭での生活が困難な子どもを支援する施設として広く知られています。他には、「児童扶養手当」や「児童館」などのように、学校に関連する活動や施設の名称などにも使われることがあります。
「児童」の例文
- 児童の安全を守るために、登下校時の見守り活動が行われています。
- 学校では、児童向けにさまざまなイベントが企画されています。
- 児童館には、放課後に遊びに来る子どもたちが集まります。
- 児童が使用する教材は、年齢に応じた内容になっています。
- 児童の心身の成長を支えるため、専門家の指導が重要です。
「小児」と「児童」の違い

「小児」と「児童」の違いは、使用される文脈と対象年齢にあります。以下の表で、違いを整理しておきましょう。
| 項目 | 小児 | 児童 |
|---|---|---|
| 対象年齢 | 乳児から小学生前後まで | 主に6歳から12歳までの小学生 |
| 使用される分野 | 医療、福祉、保健など | 教育、学校関連、行政 |
| 具体例 | 小児科、小児用薬品、小児保健 | 児童会、児童向け教材、児童館 |
| 意味 | 幼い子どもを広く指す | 学校に通う子ども、特に小学生 |
「小児」は、一般に幼い子供、特に生まれてから数歳までの年齢層を指します。医学的には、「小児」は0歳から15歳までの子供を広く指しますが、特に生まれてから数歳の段階を強調する場合が多いです。
例えば、「小児科」という科目は、子供の病気や発達に関する診療を行う科であり、ここでの「小児」は非常に幼い子供を指すことが多いです。
一方、「児童」は、一般に小学校に通う年齢層を指します。日本では、児童は通常6歳から12歳の間に位置する年齢層に該当します。
学校や教育機関の文脈でよく使用され、例えば「児童福祉」や「児童教育」などの分野で使われます。日本の法律や行政でも、「児童」という言葉は小学校低学年から高学年くらいまでの子供を指すことが一般的です。
このように、「小児」と「児童」の違いは、主に年齢層と使用される文脈にあります。「小児」は医療や福祉に関連した言葉で、年齢範囲が広く、幼児期の子供に焦点を当てることが多いのに対し、「児童」は教育や行政の分野でよく使われ、小学校に通う子供たちを指すことが一般的です。
「小児」と「児童」の使い分け
「小児」と「児童」の使い分けについて、以下のように説明できます。
① 医学的な場合
医療や健康管理などの医学的な分野では「小児」を使います。特に「小児科」などの専門用語において、年齢層としては0歳から15歳までの子供を指すことが一般的です。医療的には、特に幼い子供(乳幼児)を指す場面が多く、発育や病気の観点からこの区分が重要です。
② 教育や福祉の場面
教育や福祉に関する場面では、「児童」を使います。例えば、「児童教育」や「児童福祉」など、教育機関や福祉に関連する文脈では、小学生の子供たちを対象にしています。学校での教育活動や福祉サービスに関連する場面で「児童」という表現が一般的です。
③ 年齢層や文脈に応じて
「小児」と「児童」は、年齢や用途に応じて使い分けられます。「小児」は広い年齢層を指すため、年齢に関わらず医療や発達に関する話題で使いますが、「児童」は特に学校教育に関わる年齢層(6歳〜12歳)を指すため、教育的な場面では「児童」を使うのが適切です。
まとめ
今回は、「小児」と「児童」の違いについて解説しました。
「小児」は主に医療や福祉、保健の分野で使われ、乳児から15歳未満の子どもを指します。一方、「児童」は学校教育に関連した言葉で、小学校に通う6歳から12歳の子どもを指します。
このように、両者は使用される場面が異なるため、適切に使い分けることが重要です。医療や福祉では「小児」を、教育や福祉活動に関連する場合には「児童」を使うと覚えるとよいでしょう。
本記事と合わせて、以下の関連記事を読むと、より理解が深まります。